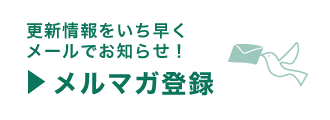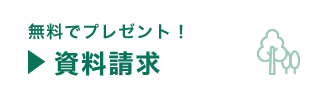福井県坂井市でEM農法を取り入れた特別栽培野菜を育てている、vegeマリコです。
「化学肥料や農薬、ホルモン剤を使わずに、安心で安全な野菜を作りたい。そしてその野菜を必要としている方々に届けたい。」という思いから、特別栽培の認定を受けた野菜を育てるようになりました。
小規模農家ですが多品目を栽培しています。
EM農法を活用することで、野菜がミネラルを効率よく吸収し、ストレスなく成長できる土壌を作る努力をしています。
私の畑には、野菜に害を与える虫も、それを捕食する虫も共生していて、畑に自生する雑草は、昆虫たちの住処となっています。彼らが活動を終えたたらこの雑草で草堆肥を作り、その堆肥は再び畑の土へ還るのです。
私は自然のサイクルが巡るこの理想的な環境で野菜を育てています。
以前「無農薬トウモロコシへの挑戦!」と題し、3回にわたってその栽培方法を紹介させて頂きました。
無農薬トウモロコシへの挑戦!<第1回>|【北陸EM普及協会】
今回は私の玉ねぎ栽培について、どのようにEMを活用しているか、どんなことに気をつけているかをご紹介します。
目次
vegeマリコおすすめの玉ねぎ~こだわりの2品種
vegeマリコで育てている玉ねぎは、以下の2つです。
■赤玉はフレッシュレッド
フレッシュレッドは赤の発色が良く、甲高でまんまるな形の中性種です。市販されている種や苗は扁平型が多いですが、甲高の赤玉は見た目にも美しく、料理に適しています。
生食の際にはスライスしても形が崩れにくく、辛みも少ないため、煮物や炒め物の彩りとしても適しています。この点を生産者に伝えると、多くの方が納得します。私はお客様にもまんまる甲高赤玉の良さをアピールしてお勧めしています。

■白玉はネオアース
ネオアースは辛味がなく、甘い味わいが特徴の中晩性種で、玉も400gと大きく、クリーム色の肌がきれいな品種です。
色ツヤが良く、長期保存が可能な点も魅力の一つ。外側の皮は薄茶色で実の締まりが良く、こちらもまんまるとした形状をしています。生のままスライスしてサラダとしても美味しく、肉厚で食べ応えがあります。

EMを活かした土作りだからミネラルが効く
■土作りのためのミネラル資材
土壌には、EM活性液、EM・3(光合成細菌)、EMボカシを主に使用します。
EM資材やひじきなどの資材。どれも土にミネラルとうま味をプラスする大事なもの
そのほかには、ニームエース、硫酸カルシウム、炭酸カルシウム、貝化石、カキガラなどを使用し、ミネラルの種類を増やします。また、EM活性液に漬け込んだひじきやアカモクなどの海藻、稲や麦のワラ、ラクトヒロックス、米ぬか、フルボ酸なども様子を見て適宜使用し、土づくりをし、畝たてをします。

■ポイントその1.海藻(ひじき)
2018年から土作りの際に乾燥ひじきの残渣(ざんさ)を投入するようになって、玉ねぎが甘い、うま味があると言われ始めました。また有機物を分解させるためにラクトヒロックスもこの頃から使い始めました。そして、バチルス菌のエサとして必要な、米ぬかもたっぷりすき込む事にもなりました。
アカモクは6月に採れるのでEM活性液と光合成菌につけておいたものを使います。

■ポイントその2.フルボ酸
有機栽培では根がよく発達し、土から養分をしっかり吸収すると読んだことがあります。しかし、毎回の栽培でさまざまな資材を投入する中で、本当にこれだけのものが必要なのか疑問を持っていました。
ある日、本を読んでいてフルボ酸についての記述を見つけました。その本には「有機栽培をしていると、土の中のミネラル(鉄、銅、カルシウム、マグネシウム、亜鉛など)が他の分子とくっついてしまい、植物の根が吸収しにくくなる」と書かれていました。
これは、まさに私の疑問そのもので、その答えがフルボ酸にあることが分かりました。
ロッキー山脈の地下2000メートルの地層から採れるフルボ酸は「キレート」(ギリシャ語で「カニのはさみ」という意味)という作用を持ち、何かとくっついているミネラルを分離して単体にしてくれるそうです。これにより、土壌中のミネラルが植物の根から吸収されやすくなるということがわかって、以来、私の野菜作りには欠かせない資材となりました。
私が住む福井県坂井市の坂井平野では、米だけでなくスイカやメロンなどの慣行栽培も行われていますが、これらの農場でもフルボ酸が使われているようです。より美味しく甘い作物を作るための工夫だと思われます。
<施用資材詳細まとめ>
| 資材名 | 量(m²あたり) | ||
| EMボカシ | 500g/m² | ||
| EM活性液 | 500倍 | 定植後数回の葉面散布 | |
| ニームエース | 60g/m² | 定植後、根切り虫にやられないため | |
| 硫酸カルシウム (カルアーズ) |
30g/m² | 水にとけやすいカルシウム「ミネラル先行、窒素後追い」 | |
| 炭酸カルシウム | 苦土石灰 | 60g/m² | 水にとけにくいミネラルの種類を多くするため3種使用 |
| 貝化石 | 30g/m² | ||
| カキガラ | 30g/m² | ||
| ひじき(乾燥) | 30g/m² | 手に入ったらアカモク、ワカメも追加。 | |
| ワラ(稲・麦) | 有機物を分解してもらうための枯草菌、バチルス菌(ラクトヒロックス) | ||
| ラクトヒロックス | 2g/m² | ||
| 米ぬか | 670g/m² | 米ぬかはバチルス菌のエサになるので必ず投入 | |
| フルボ酸 | 90g/m² | ||
試食会1位!“からくない、甘い、うまい”の秘密は土の中
さて、ここからは玉ねぎの味についてです。ある日、野菜作りの仲間たちと集まり、白玉ねぎを持ち寄って5人分をスライスし、手づかみで試食をしました。その結果、私の玉ねぎは「辛みがまったくない」「甘い」「うま味がある」と高評価をいただき、1位に選ばれました。私は、同じような栽培方法でも味に差があることに初めて気づき、大変驚きました。

2位の玉ねぎは、わずかに辛みがありうま味が少なかったとの所感を聞き、玉ねぎ栽培の方法を比べたところ、土作りの時のフルボ酸の使い方に違いがあることが分かりました。私は90g/m²のフルボ酸を投入していますが、2位の方はボカシ肥を作る際にフルボ酸を加えているそうです。つまり、土に投入されるフルボ酸の量の違いが、味の差につながったのではないかと思われます。私の場合は、フルボ酸のキレート効果が十分に発揮されているようです。
アミノ酸(=EMボカシ)、グルタミン酸(=乾燥ひじき)、イノシン酸(=EMボカシに入れる魚)、この3つは、美味しい料理を作るための三大要素ですが、畑の土づくりにも通じているとは驚きです。
EMを定期的に散布していることにより土壌の団粒構造が出来ているために、施用しているミネラル資材やフルボ酸が効果的に働いてくれるのは、のではと感じています。微生物は土壌の栄養素の変換や有機物の分解に重要な役割を果たしています。微生物の活動が不十分だと、ミネラルが適切に変換されず、植物が利用しにくいそうです。
私の畑の土作りは、EMをベースにしてミネラル資材、フルボ酸がそれぞれ効率よく働く環境が整っており、各資材の相乗効果で美味しい野菜が育つのだと思っています。
トウ立ちを防ぎ、甘さを引き出す栽培法
■トウ立ちさせないための工夫
トウ立ちとは、玉ねぎの成長過程で花径(トウ)が伸びて、花を咲かせようとする現象です。
トウ立ちすると、玉が固くなる、味が落ちる、玉のサイズが小さくなる、玉ねぎの中心に芯が出来て保存性が悪くなる、などの悪影響があります。
そのため、玉ねぎが花を咲かせないように気を付けなければならないのです。
■トウ立ちの原因と対策
トウ立ちは、肥料切れや積算温度が原因とされていますが、私は植物が命の危険を感じたときに、「早く花を咲かせ、種を作り子孫を残さねば!」と生殖ホルモンのスイッチが入ることが主な原因ではないか、と考えています。
そのため、肥料切れや不足がないように、地温が上がりすぎないように注意することが大切です
■肥料切れを起こさないための肥料の管理
私の場合は、前作の追肥や残肥を考慮し、基本的にボカシの元肥500g/m²を施しました。
12月末から1月10日にかけて1回目の追肥200g/m²、2月中頃に2回目の追肥300g/m²を行います。これで合計約1kg/m²の肥料を確保します。
前作では数回追肥をしており、残肥を考えた場合は元肥500g/m²を350g/m²にして、2回の追肥で最終的に800~1kg/m²になるようにします。
■追肥での失敗
過去、肥料切れで失敗した経験があります。
当時、150mの穴あきマルチを使用しており、追肥として苗の穴に1~2つまみくらいEMボカシⅡ型を入れましたが、実は必要な量の1/2~1/3だったのです。計算したところ、このときまでに入れたEMボカシⅡ型の総量は700g/m²でした。
結果として植えた苗のうち25%にトウ立ちが発生してしまいました。全然肥料が入っていかなかったと反省し、計算し直して追加を穴につまみ入れ、以後は追加するEMボカシⅡ型の量について気をつけるようになりました。
■追肥しやすいマルチの工夫
畝のマルチの片側は、しっかり押えピンで止めておき、もう片側ははずしやすいタイプ(取っ手がついているピン)にするのがおすすめです。いざ追肥の際には片側だけピンをはずしてマルチを浮かし、そこから勢いよくボカシ肥を投げ入れると畝全体に肥料が入ります。
■トウ立ちさせないための温度対策
玉ねぎは低温に強く、高温に弱い性質があります。ここ、福井県では近年、積雪、残雪もなく春は異常な高温の日が続きます。
そのため、2月中頃の2回目の追肥時には、マルチを外します。15cmの穴から玉ねぎの茎・葉がスルスルとなんとか引っかからずに抜けるタイミングが目安です。

“からくない”に込められた、最高の褒め言葉 。私の原動力になったプロのひとこと
私の玉ねぎをランチなどで使ってくださっているシェフからは「からくない」「甘い」「うま味がある」「玉が締まっている」と高評価をいただき、また、ベーグル店からも「からくない」「甘い」「ほかで買っているものとは別物」お褒めの言葉を受けました。
お客様からは「うま味とはカツオ節を食べた後の余韻」と表現され、これ以上の誉め言葉はありません。

昨年まで慣行栽培をされてきた方が、今年は私の栽培方法を参考にして、EMボカシとひじきを使用したところ、からくない玉ねぎができたそうで喜んで報告してくれました。
この方のほかにも「おいしい野菜が作りたい」と私の元に野菜作りを習いに来た青年が同じように土づくりをして玉ねぎを栽培しました。
1年目は「見た目は良かったけれど味が苦かった」そうです。
しかし、2年目には見た目も味も格段に良くなり、「からくなくて美味しい玉ねぎができた」とのこと。
EMを活用した土づくりは、続けるほどに土が整い、玉ねぎの味にもそれが表れてくるのだと、私自身あらためて実感しました。
このように、土づくりからじっくりと手をかけて育てた玉ねぎだからこそ、私は味だけでなく栄養の面も大切にしたい。
玉ねぎは、スライスしてから水にさらしたり漬けたりすると、大切な栄養素が流れてしまいます。
だからこそ、調理の手間なくそのまま生で食べられる、子どもたちにも食べやすい美味しい玉ねぎを、これからも作り続けていきたいと願っています。