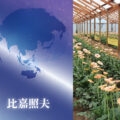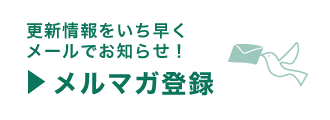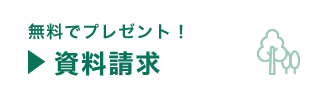グアテマラにおけるEMの普及は、EARTH大学の卒業生を中心に、いまや全国各地へと広がりを見せています。
導入初期は河川の浄化に焦点が当てられ、特に首都近郊のアマティトラン湖では、EMを添加した水質改善の試みが本格的に展開されました。EMが増殖しやすい環境をシステムとして整備することで、湖全体の自然浄化を促進。その結果、流域の生態系が回復し、水辺の環境が豊かさを取り戻すという成果が報告されています。
今回紹介するのは、花卉栽培が盛んなグアテマラの高原地域での活用事例ですが、コロンビアのカーネーション栽培の活用方法が中南米のすべてに行き渡っています。
グアテマラの農家では化学資材を減らしながら、持続可能で収益性の高い生産を実現しています。
EM技術で花の品質と収量が向上しました。
以下、現地からの報告です。

化学資材に頼らない花卉栽培を目指して
首都グアテマラ市から北西に約32km、標高1,800mに位置するロマ・アルタ村。この地域は、バラやカーネーション、ユリ、ガーベラ、カスミソウ、キクなどの栽培が盛んで、主にメキシコ、欧州、米国、中東などに輸出されています。地域に根ざした産業として、経済的にも社会的にも重要な役割を果たしてきました。

しかし、農家たちは深刻な課題にも直面していました。
-
化学肥料・農薬への過度な依存
-
土壌の劣化と微生物バランスの崩壊
-
花の品質低下と日持ちの悪化
こうした問題は、生産性や収益性の低下だけでなく、環境や健康への影響も懸念されていました。
EMで変わる!花の健康と地域の未来
EMの導入により、農家たちは持続可能な栽培への転換を進め、EM・1を用いた以下のような対策が行われました。
-
土壌環境の改善(微生物バランスの向上)
-
根の発達促進と病気予防
-
鶏ふんとの併用による土壌の栄養バランス調整
こうした取り組みによって、健康で力強い母株の育成が可能となり、苗の生産性や品質も向上。15日ごとの安定した収穫が実現し、生産サイクルがスムーズに回るようになりました。

数値が物語るEMの成果
 その結果、EM技術を導入した効果は、以下のような明確な数値で裏付けられることとなりました。
その結果、EM技術を導入した効果は、以下のような明確な数値で裏付けられることとなりました。
-
化学肥料の使用量を50%以上削減
-
農薬の使用量を最大75%削減
-
植物の根が強化され、花の形状や色味、保存期間が大幅に向上(最大20日間)
-
一株あたりの茎数が増加し、枯死率も低下
-
肥料臭やハエの発生が抑えられ、作業環境も改善
-
成長期間が15日短縮、年3回から4回の収穫が可能に
-
資材費の削減と収入の増加により、1サイクルあたりの収益が20%アップ
-
防カビ剤・殺菌剤の使用ゼロでも安定した品質を維持

世界とつながるEMの輪
2024年には、ロマ・アルタ村で「再生型農業に関する国際セミナー」が開催され、グアテマラの農家たちが中南米各国の参加者にEM技術の成果を紹介しました。現地での栽培実例や改善効果に、参加者たちは驚きとともに深い関心を寄せていました。

EMは単なる技術ではなく、人と環境、そして未来をつなぐ【 善循環 】の象徴として、確かな歩みを続けています。グアテマラの取り組みは、日本の農業にとっても新たなヒントを与えてくれるでしょう。
(出典:「花卉栽培における化学薬品の削減と収益向上|EM GROUP JAPAN」)
>導入事例の詳細はこちら(EMROサイト)