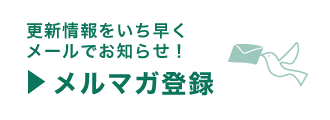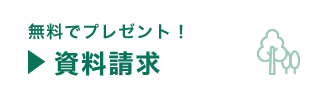病害虫予防は土づくりから
家庭菜園といえば夏野菜の栽培が定番ですよね。その中でも一番人気はやはりトマトではないでしょうか。そこで今回は、EM柴田農園のトマトづくりを通して、私たちが実践している病害虫予防の方法をご紹介したいと思います。
私の農園では「栽培期間中、化学肥料と農薬を使っていません」と宣言しています。化学肥料はもちろん、有機JASで認められている農薬も使いません。そこで心がけているのは、『春先の土づくりを徹底して、病害虫に負けない元気な野菜づくりをすること』です。
その方法は【連載 Part.2 第4回 ~春になったら土づくり~ 】で紹介しています。

毎年この方法で土づくりをし、5月に定植をしてから7月中旬まで病害虫の影響はほとんどなく、元気に育ちます。これは、春の土づくりがいかに重要かを物語っているように感じます。
トマト栽培では、病害虫が出てから対処するのではなく、あらかじめ出にくい環境を整えておくことが大切です。
そうした日々の積み重ねこそが、健やかな野菜づくりにつながるのではないでしょうか。
こうした考え方のもとで、私たちが特に注意しているのが「梅雨」の時期です。
湿度が上がるこの季節は、病害虫のリスクが一気に高まるタイミング。
続いては、EM柴田農園で実践している梅雨時の具体的な対策をご紹介します。
病害虫予防の最大のハードルは梅雨
植物も私たちと同じで季節の変わり目が苦手なもの。特にトマトは湿度や温度変化に影響を受けやすく、梅雨を越すのが一番のハードルです。
この時期に病気や害虫が一気に増えるのは、ジメジメとした環境がトマトにとって負担になるからです。
そこで私たちが最も気をつけているのが、「風通しをよくすること」。梅雨の間もハウス内の湿度をできるだけ下げ、風が抜ける環境を保つことで病害虫のリスクを抑えることができます。
それでは、実際にどのような対策を行っているのかをご紹介しましょう。
ハウス農家の雨との闘い
関東地方の天気予報ではよく気象予報士さんが「北部山沿いでは急な雷雨に注意してください」と言いますよね。私の農園は栃木県那須塩原市、まさにその北部山沿いにあります。突然激しい雨が降ったかと思えば、また太陽が顔を出す。そのたびにハウスのサイドのビニールを下ろしたり、上げたり…。雨は防ぎたい、でも換気もしたい。天気が変わりやすい日は、一日に何度も繰り返すことになります。過去にはサイドのビニールを下ろすのが間に合わず、突然の雷雨でハウスの通路がぬかるみになったことがあります。そこで突然の大雨対策として、ハウスの内側に雨樋を設置。これが予想以上に効果的でした。
家庭菜園ではここまでの設備は難しいかもしれませんが、急な雨の前には支柱の固定や風通しの調整など、少しでも雨を受け流す工夫を意識してみると良いかもしれません。


風通しを良くするための株間の工夫
湿度対策で効果的なのは風通しを良くすることです。トマトの株間は45㎝から50㎝が一般的ですが、私は70㎝にして葉ができるだけ重ならないようにします。風通し重視の株間です。
※この時期はすでに植え付けが終わっている方も多いかと思いますが、来年のトマトづくりの参考としていただけたらと思います。

害虫対策のネットについて
風通しを良くすることで湿度対策にはなりますが、その分、外から虫が入ってくるリスクも高まります。そんなときに活用できるのが、ネットを使った害虫対策です。
多くのトマト農家さんは、ウイルスを媒介するコナジラミという小さな虫対策のために、網戸より目の細かい目合い0.4㎜のネットでハウス全体を覆っています。ただし風通しが悪くなるため、トマトにとって良い環境とは言えず、別の病気を誘発する原因にもなりかねません。
EM柴田農園では毎年、梅雨明け以降も大きな病害虫の被害はありませんでしたが、昨年だけはオオタバコガの幼虫の食害で何本も被害を受けました。そこで今年は初めて、予防策として目合い9㎜のネットでハウス全体を囲みました。オオタバコガの対策にどれだけ効果があるかはわかりませんし、コナジラミなどの小さな虫対策にはなりませんが、風通しと換気を重視した結果、このサイズに落ち着きました。

朝晩のEM散布が病害虫予防の鍵

風通しやネットなどの工夫に加えて、私が長年続けているのがEMの活用です。農薬を使わない栽培では、この日々の積み重ねがとても大切になります。
毎年、無農薬で7月上旬から霜が降りる11月末まで収穫ができているのは、50倍希釈のEM散布の効果ではないかと私は考えています。「毎日EM散布ですか?」と驚く方も多いのですが、ハウスの横に動力噴霧機が設置されているので大きな負担ではありません。夏はあまりの爽快感に、トマトだけでなくつい自分にも散布したくなります。

家庭菜園ではなかなか同じようにはいきませんが、朝晩のこまめな散布を習慣にすることで、病害虫のリスクを少しずつ抑えられるのではと思います。
農薬を使わない農法では、病害虫が発生してから対処するのは難しいものです。だからこそ、病気や害虫が出にくい環境づくりを心がけることが大切になります。
これは、病気になってから薬で治すという発想ではなく、日頃から食事や生活習慣に気をつけて健康を維持する――そんな考え方に近いかもしれません。
EMを使った朝晩の散布や、栽培初期の土づくりへの活用も、そうした“日々の積み重ね”のひとつとして、私自身とても効果を実感しています。
野菜づくりは一朝一夕ではいきませんが、少しずつ積み重ねていくことで、きっと健やかでおいしい作物が育ってくれるはずです。

ところで、読者の方は「この対策で病害虫予防ができたのだろうか?」 「無農薬で本当に長期間栽培できるのだろうか?」――そんな疑問をお持ちかもしれません。
そこで今後、梅雨を越し、厳しい猛暑も乗り越えた秋以降に、あらためてご報告できればと考えています。
良い結果をご報告できるといいのですが……うまくいくかは神のみぞ知る、ですね。
できることを一つひとつ積み重ねて、またこの連載でお伝えできればと思っています。
【柴田さんへの質問はこちらから】→<Web Ecopure お問い合わせフォームへ>
<PROFILE>

柴田和明(しばたかずあき) 会社退職後、約2年間栃木県農業大学校で農業を学び、その後トマト農家で1年間研修を受け就農。 柴田知子(しばたともこ) 会社退職後、東京農業大学(世田谷区)オープンキャンパスのカレッジ講座で野菜や果樹の育て方、スローフード、発酵などの講座を受講。EM柴田農園では、種まきから仮植、種取りなどの細やかな作業を担当。