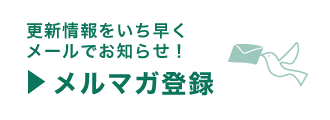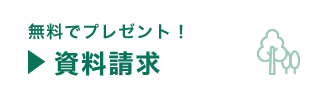目次
農家に必ずある苗を育てるハウスとは
多くの農家では、苗を育てるための「育苗ハウス」を備えています。種まきから定植までの間、苗を雨風や病害虫から守り、安定した環境で育てるための大切な場所です。
寒い時期でも、ビニールなどの被覆資材(ハウスやトンネル)で外気を遮り、温床線(地面や苗の下に敷く電熱線)などで地温を確保することで、苗の生育に適した温度環境を保つことができます。

発芽に適した温度管理の大変さ
レタスやホウレンソウなど15~20度の低温で発芽するものを除けば、ほとんどの野菜は20~30度で管理する必要があります。
ところが近年の夏は『地球温暖化』を通り越し『地球沸騰化』とまで言われるような暑さです。
ハウス内の温度を上げることは比較的しやすいのですが、下げるのは難しく、夏場の気温が高い時期は特に苦労します。育苗ハウス内は外よりさらに高温になるため、種がうまく発芽しないこともあります。私の育苗ハウスにはエアコンのような冷房設備はないため、真夏の温度管理には扇風機や遮光資材を使って対策するしかなく、とても大変です。
白菜の発芽を成功させるプロ農家の工夫
冬の鍋料理や漬物などでは欠かすことが出来ない白菜を家庭菜園で種から育てたいと思っている方もいるのではないでしょうか。地域や品種にもよりますが、私の農園がある栃木県では11月以降に収穫するためには8月の猛暑の中で種をまきます。そのため、暑さ対策はとても重要です。
私の知り合いの白菜農家さんは、セルトレイに種まきをしてから送風機で風を送り、苗床の管理をしていました。
下の写真は送風機を使用してタマネギを乾燥しているシーンです。プロ農家はこのような送風機を使って温度を下げる工夫をしています。

夏の発芽は育苗ハウスではなく…
夏の暑さが厳しい時期、育苗ハウス内はどうしても高温になりすぎてしまいます。
そこで私が見つけたのが、家の横にある森の中で種を発芽させる方法です。

画像のように木が何本か立っていて風通しがよく、直射日光が当たらない半日陰のような場所―こんな環境があれば、家庭菜園でも真似できます。育苗ポットやセルトレイに種を撒き、水やりをしたらすぐに森の中に置く。すると3~4日で発芽します。発芽促進のためにも水やりにはEM希釈液を使いましょう。
重要なのは発芽したら日当たりの良い場所に移すこと。そのままにしておくと光を求めて伸びすぎてしまい、もやしのように徒長してしまいます。
農家なら発芽後はすぐに育苗ハウスに移しますが、家庭菜園の場合はなるべく風通しの良い適度な日差しが入るところに移動させて、苗の様子をみながら育ててみてください。

発芽したあとの管理と鉢上げのタイミングなど、詳しくはPart.2 第5回「苗づくりは子育てに似ている」をご覧ください。
2~3日の外出時、育苗は”森”におまかせ
小まめな管理が必要な育苗中は外出をなるべく控えていますが、写真のようにある程度の大きさに生長したタイミングであれば森の中に置いて1泊程度の外出をすることがあります。森の中では直射日光が避けられ、鉢の乾きがぐっと遅くなります。
雨が当たらないよう屋根をつけておけばさらに安心ですが、私の経験では大雨が降っても木の枝が雨をさえぎるため、苗にはほとんど影響がありませんでした。ただし、シカ対策のためのネットは必須です。

夏の発芽のカギは”日陰×風通し”
発芽までなら太陽光は必要ない野菜が多いので、森がなくてもベランダや駐車場の一角、北側の軒下などをうまく活用すれば、真夏の発芽・育苗もうまくいきます。
“夏の発芽は森の中”──自然の力を味方につけた、工夫と経験の積み重ねからの発想です。日陰と風通しさえ確保できれば、特別な設備がなくても大丈夫。
「夏の苗づくりはできない」とあきらめていた方も、ちょっとした日陰スペースでチャレンジしてみてください。
ネコは涼しいところをよく知っているらしいので、ネコに聞いてみるのもいいかもしれませんね。
【柴田さんへの質問はこちらから】→<Web Ecopure お問い合わせフォームへ>
<PROFILE>

柴田和明(しばたかずあき) 会社退職後、約2年間栃木県農業大学校で農業を学び、その後トマト農家で1年間研修を受け就農。 柴田知子(しばたともこ) 会社退職後、東京農業大学(世田谷区)オープンキャンパスのカレッジ講座で野菜や果樹の育て方、スローフード、発酵などの講座を受講。EM柴田農園では、種まきから仮植、種取りなどの細やかな作業を担当。